鉄鋼材料と熱処理条件 6章
6.機械構造用鋼の焼入れ焼戻し
(1) 焼入条件の選定
機械構造用鋼の持っている最高の特性を発揮させるためには、理想的には焼入れによって完全なマルテンサイト組織にすることである。機械構造用鋼はすべてが亜共析鋼であるので、適正焼入温度はA3変態点よりも30~50℃高い温度であり、鋼種が決まれば自ずと焼入温度も推測がつく。考え方としては処理物が大物の場合は高めの温度を選定するとよい。なぜならば、大物は焼入れ冷却のときの冷却速度が遅くなるため焼きが入り難くなるが、高めの温度で加熱すると焼入性が向上するため、焼きの入りやすさの点で有利になるからである。また、焼入れ冷却の際に水のような冷却能の大きい冷却剤を使用する場合は低めの温度を選定し、冷却能の小さい冷却剤を使用する場合には高めの温度を選定するとよい。
例えば、S45CのA3変態点は780℃位であるから、焼入温度範囲は820~870℃が理想である。図1.8に各温度から焼入れしたときのS45C(直径25mm、高さ15mm)の顕微鏡組織写真を示すように、この焼入温度範囲から焼入れした場合にのみ正常なマルテンサイト組織が得られている。以下に図1.8を用いて各温度から焼入れした際の金属組織と特性を説明する。なお、この内容については同寸法の他の機械構造用鋼でもほぼ同様の結果が得られる。また、処理物の大きさが異なると、鋼種間の質量効果も異なることを考慮しなければならない。
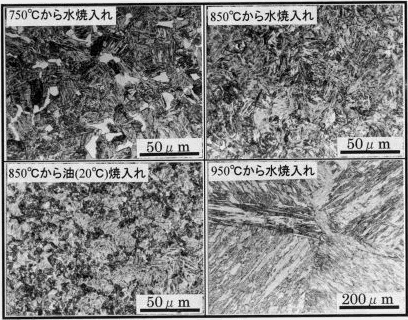
図1.8 種々の温度から焼入れしたS45Cの顕微鏡組織
①A1変態点とA3変態点の中間の温度(750℃)から焼入れしたとき
金属組織はマルテンサイトとフェライト(写真では白色部)の混合組織であり、十分な焼入硬さは得られない。平衡状態図からも明らかなように、この温度における加熱状態ではオーステナイトとフェライトの混合組織を呈している。この状態から急冷するとオーステナイトはマルテンサイトに変態して硬化するが、フェライトはそのまま室温まで維持されてしまう。
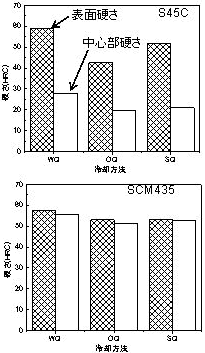
図1.9 種々の冷却剤を用いて 焼入れしたときの 表面および中心部の硬さ
②適正温度(850℃)から焼入れしたとき
この温度で加熱すると完全なオーステナイト組織になるため、急冷によって正常なマルテンサイト組織が得られている。しかし、この温度から焼入れしても冷却速度が遅くなる(室温の油による冷却)とマルテンサイトのほかに微細パーライト(写真では黒色部)も観察される。微細パーライトとは、冷却過程でセメンタイトが析出したもので、一種の不完全焼入れ部であり、焼入硬さの低下や硬さむらの原因になる。
③適正温度よりも100℃高め(950℃)から焼入れしたとき
この温度で加熱すると完全なオーステナイト組織になっているが、加熱温度が高すぎるため、急冷によって粗大化したマルテンサイト組織が得られている。このマルテンサイトはラスマルテン(板状マルテンサイト)と称されるもので、焼入硬さは最も高いが機械的性質は脆く、焼割れも生じやすいため、この温度はS45Cの焼入条件としては不適当である。
以上の内容は直径25mm、高さ15mmという非常に小さい試験片のときにいえることである。すなわち、試料の質量が増加すると冷却速度が遅くなるため、焼入性の悪い材料は図1.8のような焼入温度に依存した理想的な金属組織を得るのは困難である。とくに炭素鋼であるS45Cなどは直径が25mmであっても高さが増加すると、水冷を行っても中心部は理想的には硬化しない。
一例として図1.9に直径25mm、高さ50mmのS45Cについて、種々の冷却剤を用いて焼入れしたときの表面および中心部の硬さを示す。水冷を行っても中心部の硬さは表面よりも大幅に低い値になっており、さらに冷却剤がソルト(SQ)や油(OQ)のときは表面硬さも低い値になっている。比較のために同一寸法のSCM435についても同様の試験を行ったところ、すべての冷却剤に対して中心部まで硬化しており、S45Cよりは大幅に焼入性が優れていることが確認された。また、本図においては冷却剤の冷却能の違いも明確に現れており、水、ソルト、油の順に冷却能が優れているといえる。
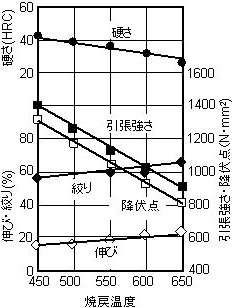
図1.10 SCM435の焼戻温度と機械的 性質の関係(焼入温度:850℃)
(2) 焼戻条件の選定
機械構造用鋼は、焼入れ後の焼戻しによって機械的性質を調整して用いられている。多くの機械構造用部品にはじん性が要求されるため、機械構造用鋼の焼戻しは500~650℃の高温で行われるのが普通である。しかし、高い引張強さを要求される場合には、それよりも低い温度で焼戻しを施すこともある。図1.10は850℃から焼入れ後、種々の温度で2時間焼戻ししたSCM435について引張試験を行った結果である。焼戻温度が高いほど硬さと引張強さおよび降伏点は低下するが、伸びおよび絞りは高くなり、じん性が向上することが分かる。なお、他の機械構造用鋼もすべて同様の傾向を呈する。
図1.11に850℃から焼入れ後550℃で焼戻ししたSCM440の顕微鏡組織を示す。この顕微鏡組織に関しても他の機械構造用鋼も同様であり、顕微鏡組織では鋼種を判別することはできない。このときの金属組織は通称ソルバイトと呼ばれており、走査型電子顕微鏡像からも明らかなように、フェライト生地の中に多量のセメンタイト(微細粒子)が析出している。このソルバイトはじん性に富んでおり、機械構造用鋼の標準的な調質組織である。
また、350℃位の温度で焼戻したときの金属組織は通称トルースタイトと呼ばれており、フェライトと微細なセメンタイトの混合体である。機械構造用鋼はこの温度で焼戻しされる例はほとんどないが、ソルバイトよりも硬く、酸にエッチングされやすいので、金属組織を現出する際には低濃度のエッチング液を用いるほうがよい。
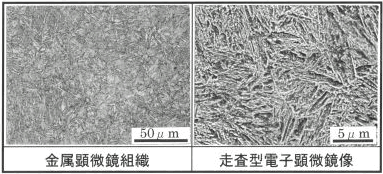
図1.11 850℃から焼入れ後、550℃で焼戻したSCM440の顕微鏡組織

